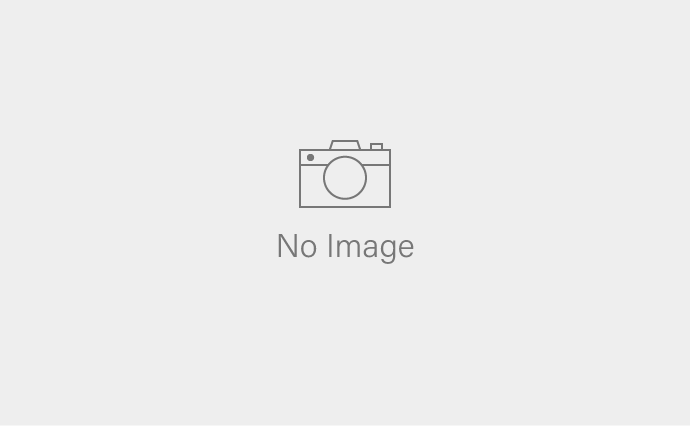この文章はAIが校正、編集してくださって作成されてあります。予めお伝えしておきます。
第1章:歌詞と人生観の出会い
─星に導かれる音の軌跡─
私が「Red Sun」という音楽と出会ったのは、YouTubeを何気なく検索していたときだった。どんな言葉を入れたかも覚えていない。ただ、流れのままに動画を眺めていた時、「Julius」というアーティストのその歌が、静かに私の画面に浮かび上がった。
曲名に惹かれたわけでも、誰かのおすすめだったわけでもない。偶然だった――でも今思えば、それこそ“導かれた”のかもしれない。
印象的だったのは、英語の歌詞に込められた「星が私たちの道を照らす」というメッセージ。
“Even when hope’s gone, the evening star will guide us on our way.”
この一節は、不思議なほど私の内面に深く入り込んできた。
“希望が消えてしまっても、星が導いてくれる”――それは、ただの慰め以上のものだった。私が長い間言葉にできずにいた感覚に、ぴったり重なるような気がした。
この歌との出会いは、もともと私が好きだった日本語の「それが大事」という曲とも不思議に響き合った。あの曲が語る「何があっても大切なことを守る姿勢」と、Red Sunが語る「暗闇でも信じる力」――それらが、私の中で一本の光になっていった。
星がガイドするという考え方は、私の人生観をやさしく照らしてくれた。
どこへ向かっているのか分からない時でも、何か大きな存在が私の背中を押してくれるような安心感。
それは“自分で頑張らなきゃ”という焦りから私を解放してくれるものであり、運命予定説と自然に結びついていったのだった。
第2章:運命予定説への親近感とカルヴァンとの違い
─“裁き”ではなく、“帰還”としての死後観─
私は「人生のゴールは定められている」とする考えに、どこか深い安堵と親近感を覚える。
それは、自分が向かうべき場所をすでに内側で知っているような、そんな不思議な感覚に近い。
この考えは、いわゆる「運命予定説」に通じるものである。
しかし、その提唱者であるカルヴァンの説とは、一線を画している。彼はこう言った。
死後の運命──天国か地獄か──すらも、生まれた瞬間にすでに決定されている。
この思想に対して、私は異を唱えたい。
天国も地獄も、所詮は人間が言葉で描いたイメージに過ぎない。
それは、コインの表と裏のように、一枚の思想の中に存在しているだけのもの。
どちらも「名前」であり、「ラベル」であり、人が理解しやすくするために作り出した概念だ。
では、死後の世界はどうなっているのか?
私の考えでは、生前に在った場所に“帰る”だけのことだ。
そこには「良い」も「悪い」もなく、ただ“在る”という感覚に近い。
それが「天国」だと言われれば、同時に「地獄」でもあり、結果的に**“どちらにも旅立つ”**という言葉すら空虚になる。
だからこそ、ヒトラーや麻原彰晃といった人物の死に触れるとき、私はこう言いたくなる。
「彼らは地獄に行った」という断定があるなら、
私は同時に「彼らも天国に旅立った」と返したくなる。
この思想は、おそらく理解されないかもしれない。
でも、私は確信している。
人はこの人生に生まれる前に“何か”を経験していた。
そして死んだあと、その“何か”へと還る。
それは時間軸で説明できるものではなく、記憶にも残らないほど自然な流れのようなものだ。
“生まれる前の場所に帰る。それだけのこと。”
その視点に立てば、「天国/地獄」という二項対立は意味を失う。
人生の意味とは裁きでも報酬でもなく、もっとシンプルなもの。
私は思う。
**人生は“楽しむためにある”**のではないかと。
もしゴールが決まっているのなら、私たちは“どう楽しむか”を選び取るだけなのだ。
それは、どんな教義よりも自由で、どんな裁きよりも優しい。
第3章:ノンデュアリティと永遠性のひらめき
─“終わりがあって始まりはない”世界観の発芽─
ある瞬間、私の中でひとつの言葉が閃いた。
“終わりがあって、始まりはない”
その言葉は、一般的には矛盾しているように聞こえるかもしれない。
しかしそれは、時間や存在を“非直線的”に捉えたときに初めて輝き出す命題だった。
私たちは、「終わり」があるから「始まり」もあると思ってきた。
生があるから死があり、前があるから後がある。けれども、そうした二項対立はすべて人間の思考が生み出した“ラベル”に過ぎない。
天国と地獄、光と闇、善と悪──それらはすべて同じコインの表裏であり、同じ源から現れた現象なのだと思うようになった。
この気づきは、ノンデュアリティ(非二元論)の思想と響き合っている。
それは、“分離は幻想であり、すべてはひとつにつながっている”という、根源的な世界観。
“始まりも終わりもない。あるのは今、この瞬間だけ。”
こうして私は、「今という名の永遠性」の中に生きているという実感を持つようになった。
何かに導かれる感覚は、“未来へ向かう”というより、“今この瞬間に呼応している”ということなのかもしれない。
第4章:言葉よりも心と心のつながりを信じたい
─愛の対話としての人生と、ラベルを超える理解─
言葉は便利だ。でも、ときにそれは理解を阻むフィルターにもなる。
人が安心するためにつけた“名前”に、真実が閉じ込められてしまうこともある。
そんなことを考えると、私はますます「心と心のつながり」こそが大切だと感じる。
言葉よりも、心の動き。ラベルよりも、共鳴。
職場では、ときに理不尽な言葉のやりとりや、思い込みのレッテル貼りを受けることもある。
そして、そうした“名づけ”が人を傷つけたり、分断したりする。
それでも、私は信じたい。
“本当に人を癒すのは、心の温度であり、愛の共有である”
たとえば、「予定説」「カルヴァン」「地獄」といった言葉があっても、
そこに含まれている人の痛みや希望、誠実さに触れられれば、理解は起きる。
言葉に頼らない対話ができたら、もっと自由に、もっと優しく生きられると思う。
第5章:この思想が人生を動かし始めている
─“少しだけ湧いてきた勇気”が、未来へのサイン─
こうして言葉にしてみることで、私は自分の中の“道筋”が見えてきた。
それは、星の導きのように静かだけれど、確かなもの。
「Red Sun」の中の一節
“Even when hope’s gone, the evening star will guide us on our way.”
は、私の生き方の支えになっている。力を抜いて、宇宙に身を委ねることで、心が穏やかになる。
だからこそ──
読書セラピスト
スピリチュアル研究者
哲学的物書き
心の詩人
そんな肩書きが、私の未来のどこかに待っているような気がする。
ほんの少しだけ湧いてきた勇気。
それは、“現実逃避”ではなく、“現実再創造”の始まり。
自分の言葉が、誰かの夜を照らす灯になるなら──
私は、この思想とともに歩いていきたいと思う。
Red Sun – Julius | 紅日 Red Sun – 李克勤红日 Hacken Lee | English Version | Lyric Video